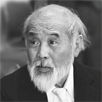
栄久庵 憲司
インダストリアルデザイナー
今回の審査会で一番苦労したところは「商品企画」という言葉
です。私は今まで漆製品を商品という眼で見ていなかっただけに
戸惑いがありました。戦後、日本は生き抜くために商品をつくっ
ては、海外から外貨を得るために四苦八苦していただけに、貴婦
人のような漆製品をどうしても商品とは思えなかったのです。
数々ある工芸品の中で、漆の処女性を求めていたのでしょうか。
確かに人の求める漆製品がなければ、産地は衰退することで
しょう。私にとってみれば、商品化とは処女性を非処女性にする
ことです。悩みました。良かったことに大賞になった作品は全く
の漆の新しい処女性を感ずるものでした。商品性があるのかと質
問されると、直ちに「ある」とは言える自信はないが、新しさは
大いにあるといえます。つまり私にとって商品性の高さは、新し
いということなのです。生地と漆が一致しています。大らかで人
の魂を広々とさせます。今までには無かったものです。漆のオリ
ジンを迷わず深めたことです。そこに新たな貴婦人性が発見でき
るのです。日本は漆を道具化しています。漆は道具文化の根底を
築いています。それに比べ西欧の漆はオブジェ化して、使い方に
天衣無縫性があって驚かされました。漆を顔料としてみているの
ですが、私には一寸馴染めないところがありました。しかし、枠
を超えて自由奔放に使っているところが刺激的で漆の概念を打破
してくれたところがよかったです。日本の漆と外国の漆が混合す
ることこそ、国際コンペの目標です。

大西 長利
漆芸家
東京芸術大学名誉教授
かねがねこの展覧会を、広く世界的視野に立点をおいて、
漆の未来性、可能性をクローズアップするものでありたいと
願いつづけてきた。今回その願いが実現化しつつあることの
実感を得た。その好例が幸いにも上位賞に並んでいる。大賞
の井川健の“時の航行”はフォルムと技術が密着していて迷い
がない。漆を象徴する黒漆の魅力を徹底して追求する姿勢に
はエールをおくりたい。金賞の戸田蓉子の“包みこむ器”は乾
漆特有の有機的でソフトなフォルム、そして朱漆が生命の誕
生を祝福するにふさわしい産湯の器といえる。よみがえらせ
たい文化だ。銀賞では韓国のラ・ユンスンの“夢”と題した黒
漆の作品は寡黙な器である。静かで強い作品とモニカ・コプ
リンさんが話した言葉が印象深かった。糸で編んで形を作り
漆で固めたもので非常に丈夫だ。本物の伝統は死なない。奨
励賞のドイツのシュミット・マンフレッドの乾漆作品“レリジ
オ”は欧州からの作品としては、精神性をきわだたせた作品
で、原初の感動を呼びさます力を秘めていた。一見技術らし
いものは見せていず、しかし器はむくな空気を発生していた。
商品開発特別賞の志奈幹雄の“服装”は最も多くの意見が交
わされた提案作品であった。布に漆は渋味のきいた独特な趣
きがある。ぜひ産業として確立してほしい。なんといっても
布と漆の固さの問題を解決することが先決だろう。甲州印伝
はその課題を見事に解決した好例がある。
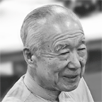
小松 喨一
金沢卯辰山工芸工房館長
漆が求められる創造の魅力を、世界に広く繋げようとする
「国際漆展・石川」が8回を数える。
今回は審査基準として、用途開発や地域の固有な技術の高
度活用といった項目が新たに示されたこともあり、論議の活
発な審査風景となった。
大賞作品となる「時の航行」は、鋭い石片のイメージを拡
大したトレイ形体のオブジェであるが、時間空間の心情を重
ね合わせ、黒漆特有の深味と光沢の流れが一体となる、完成
度の高い作品であった。
金賞の「ベビーバス」は、漆塗り産湯たらいを思い起す。
柔らかい曲面のフォルムと、ほど良い朱塗りの仕上は親しみ
を感じ、バスに赤ちゃんの柔肌の動きが連想される。漆液の
効用を含め、伝統的要素をアイデアとした楽しい生活提案の
作品であった。
商品開発特別賞は、布地素材に漆を取り入れたモード製品
であったが、身体の動きや肌と接する触覚機能の配慮に工夫
が欲しかった。漆の新たな可能性を求めた作品として評価さ
れる。
漆はエコ素材として近年注目され、その活用に広がりを期
待されるが、漆は特有の美と力を持つ素材でもある。その魅
力に秘めた価値をどのように捉えるのか、次回のコンペティ
ションに期待したい。

権 相 五
漆芸家
新羅大学校芸術大学工芸学部教授
新羅大学校漆芸研究所長(韓国)
2005年の国際漆展に続いて今年も審査員としてご招待い
ただき、誠にありがとうございます。私個人にとっても大き
な光栄に存じております。
今度の漆展の審査基準である、新しい生活提案や用途開発、
または新しい感性の表現や提案を表している作品が非常に多
くありました。
前回と比べると伝統的なものが少なく、近代的なものが多
かったです。また、デザインが前回より良くなったと思いま
すが平面作品が立体作品より良い作品がなかったことが残念
でした。
大賞は審査員それぞれみんなで話したところ、シンプルな
造形美を持っています。漆では最も難しい黒の際だちはもの
すごく良かったし用と美を兼ねた秀作です。
また、商品開発特別賞は、商品として新しい提案だと思い
ます。布地を漆で染色するとき、化学処理して布を柔らかく
すると良い開発商品になる可能性があると考えられます。
今後も漆を通した国際交流と産業の活性化、現代生活の中
で漆の価値と潤沢さが実現できるよう期待致します。
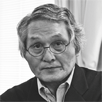
前 史 雄
漆芸家
重要無形文化財「沈金」保持者
美術工芸品は暮らしの中に単に役に立つものとしてでなく、
よりよいもの、より美しいもの、そして一段と趣向を凝らし
たものを多く生み出して来ました。それらはその時代におい
てその時代を生きた人々の生活を反映するものでした。私は
伝統的な工芸技術の保存と振興を目的とした伝統工芸の世界
で創作活動をしております。それは今日の生活に即した用と
美を兼ねそなえたものを創り上げることです。このたび二回
目の審査会出席ですが、そのような気持ちを持って臨みまし
た。国際漆展は美を強く意識した純粋美術的なものや生活の
中から生まれ出て来た用具など国内外それぞれのカラーがみ
られ、特に形態や加飾のデザインも様々でその奥の深さや幅
の広さを強く感じました。
受賞作品の「時の航行」は石の欠片をヒントにして漆黒の
艶をシャープな形態でまとめ確かな技術で美しく表現され素
晴らしい作品です。「包みこむ器」は漆の持つ特徴を生かし
たバスタブですが、昔から塗物には日持ちする性質があるよ
うです。生活用具として心暖まるメルヘンチックな感じでま
るっこい形と朱漆の美しさが表現され感動しました。
今回は商品開発を含んだテーマでの受賞枠がありました。
商品と美術工芸品の線引きが大変難しいところがありますが
「服装」は素材の特性を生かしたもので繊維の肌あいを残し
ながら漆の艶の美しさが表現されています。
今回も本展は興味を深く持って審査させていただきました。

モニカ・コプリン
ミュンスター漆器博物館館長
(ドイツ)
国際漆展の本審査に初めて参加させていただき、とても刺激になり、感激しま
した。そしてまた、この国際漆展が現代の漆アートにとっていかに大切かがわかり
ました。石川県が漆の仕事の未来を守るためにしてきた努力は、尊敬に値します。
日本と韓国からの参加者が多いなか、国外の10の国と地域から応募がありまし
た。漆が世界の工芸やデザインに材料として使われ、しっかりと自分の立場を確
立していることの表れと思います。
応募者のほとんどが、東アジアまたは東南アジアからの漆を使って仕事をして
います。しかし、フランスは18世紀に東アジアのお手本からは離れ、ヨーロッパの
漆として独自の発展をとげてきたパイオニアです。フランスでは今日でもオイル
ベースの漆を使い、革新的な、またすばらしく芸術的な創造をしています。このよ
うな漆の伝統は、ヨーロッパの他の国々では失われてしまったのに、フランスでは
継承されてきました。このことはヨーロッパ人である私にとっても、特別に大切な
ことと思われます。
私の国ドイツでは、漆にかかわっている作家はたった2人です。ドイツでは、かつ
てバロック風の漆の工房があり、東アジアの美学への文化的共感がうかがえます。
この2人の作家は漆を使い、日本の漆器のスタイルや技術をも取り入れています。
さまざまな作品の中には、伝統的な技術を使い日々の暮らしに使うものもあれ
ば、驚くような実験的な作品や、遊び心のあふれた作品もありました。大賞をとっ
た井川健さんの作品をはじめ、精神的な美しさを持つ作品もありました。金賞及
び銀賞をとった作品は伝統的な用途と清らかな普遍のデザインを合わせ持って
います。赤ちゃんが産湯に使うお風呂と洗面器ですが、漆が本来持つ静謐な美し
さが凝縮されています。漆を繊維に使った作品はまだ十分とは言えませんが、今
後の改善が期待されます。作者特有の表現に基づいた彫刻もありました。こう
いった作品を見て、現代の漆の技術的、また芸術的な可能性を感じています。
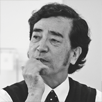
山村 真一
デザインコンサルタント
(株)コボ代表取締役社長
2008年度の国際漆展の参加作品は、手のひらにのる極小
のアクセサリーから規定寸法最大の2mに及ぶ大型のモニュ
メントに至る幅広いジャンルから200点以上が世界各国から
応募され、第一次のスライド審査と現物審査による本審査が
行われ、激しい議論を交えた結果、大賞、金賞、銀賞、奨励
賞、審査員特別賞に加え本年度から新しく設けられた商品開
発特別賞が選定された。
漆は、「ジャパン」と呼ばれるように、まさしく「日本」
を代表する伝統工芸である。さらに、石川県は日本国内にお
いても、輪島、山中の日本を代表する二大産地を擁している
ことから、日本の「漆」の総本山といえよう。この石川県金
沢市の地で、世界の漆コンペ「国際漆展」が続けられている
ことは、素晴らしいことと同時に大きな意味を持っている。
しかし、現在、日本各地の伝統工芸産地における状況は大
変厳しく、漆の業界に於いても同様であり、今回のコンペに
新しく商品開発特別賞が設けられたことは、産地の商品開発
を応援する主催者側からの強いメッセージと考えている。
この「国際漆展・石川2009」が、国内および県内の産地
に新しい風を送り込み、産地の活性化に役立つことが出来れ
ば、素晴らしい成果といえるのではないだろうか。

樋田 豊郎
秋田公立美術工芸短期大学学長
わたしは「スライド審査」にしか関与していないので、作
品を見たうえでの実感は語れないが、応募された作品や商品
の傾向という点だけでいうならば、今回は「応募者が戸惑っ
ているのではないか」という印象を受けた。
応募者は、どのようなタイプの作品・商品が、この公募
展に求められていると理解しているのだろうか。おそらく、
つかみ切れていないのだろう。いくつかの傾向、たとえば、
「伝統工芸」、「オブジェ」、「工業製品」、「クラフト」、「日
用品」の作品や商品が審査の場に並んでいた。
応募作の質は高かった。が、こう言っては失礼だが、どれ
もがその傾向を徹底的に極めているとは思えない。多くの応
募作は、いくつかの傾向を折衷していた。伝統漆芸を見たけ
れば、日本伝統工芸展を見るにしくはない。多くの観覧者は
そう感ずるだろう。
どうやら審査されているのは応募者ではなく、「国際漆
展・石川」の企画者の方なのではないか。応募者は多傾向の
作品・商品を出してみながら、企画者の意図を汲み取ろうと
しているかのようである。
今回企画者は、新しく商品開発特別賞を設けて、公募展の
趣旨を明確にしていこうとする姿勢が見られた。しかし今後
は、さらにその議論を進め、「国際漆展・石川」が、目標と
して何に向かっていくべきなのか、応募者や外部に対してよ
り明確に説明していく必要があるだろうと感じた。自戒の念
も込めて…。
事務局
国際漆展・石川開催委員会事務局
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館4階 (財)石川県デザインセンター内
TEL(076)267-0365 FAX(076)267-5242
http://www.design-ishikawa.jp/
Secretariat
The Secretariat Office of the Executive Committee
The Ishikawa International Urushi Exhibition
c/o Design Center Ishikawa
2-20 Kuratsuki, Kanazawa, Ishikawa 920-8203 JAPAN
Tel: +81-76-267-0365 Fax: +81-76-267-5242
